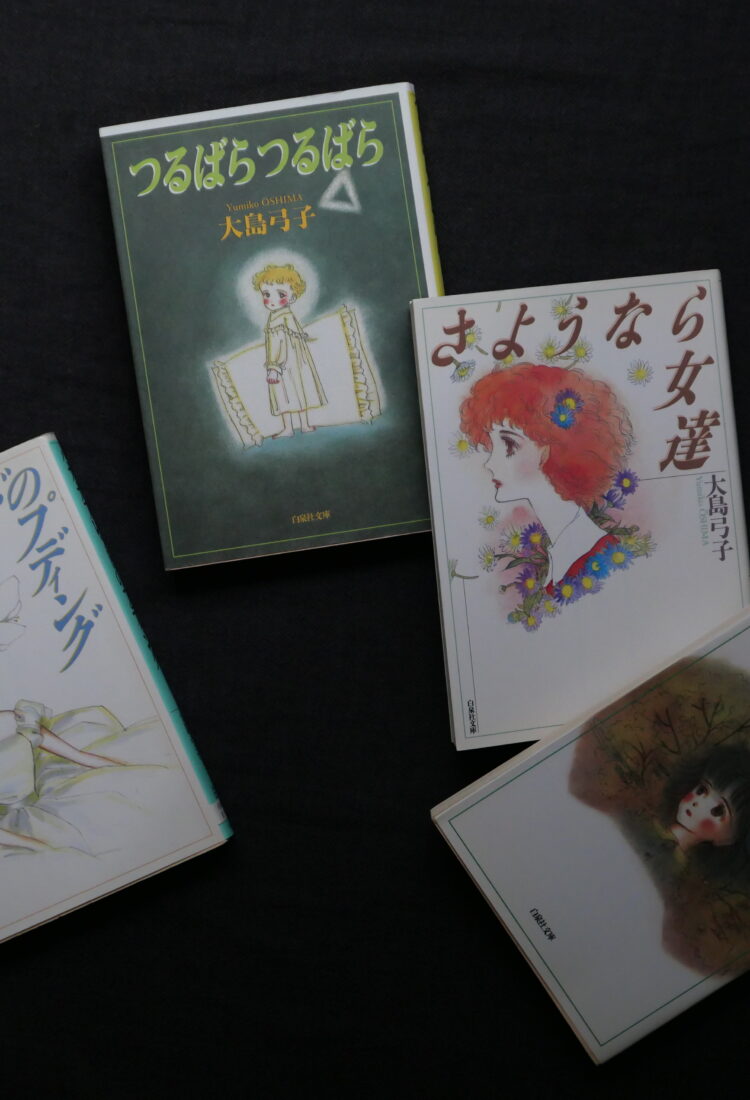▼アーユルヴェーダ | 第2回
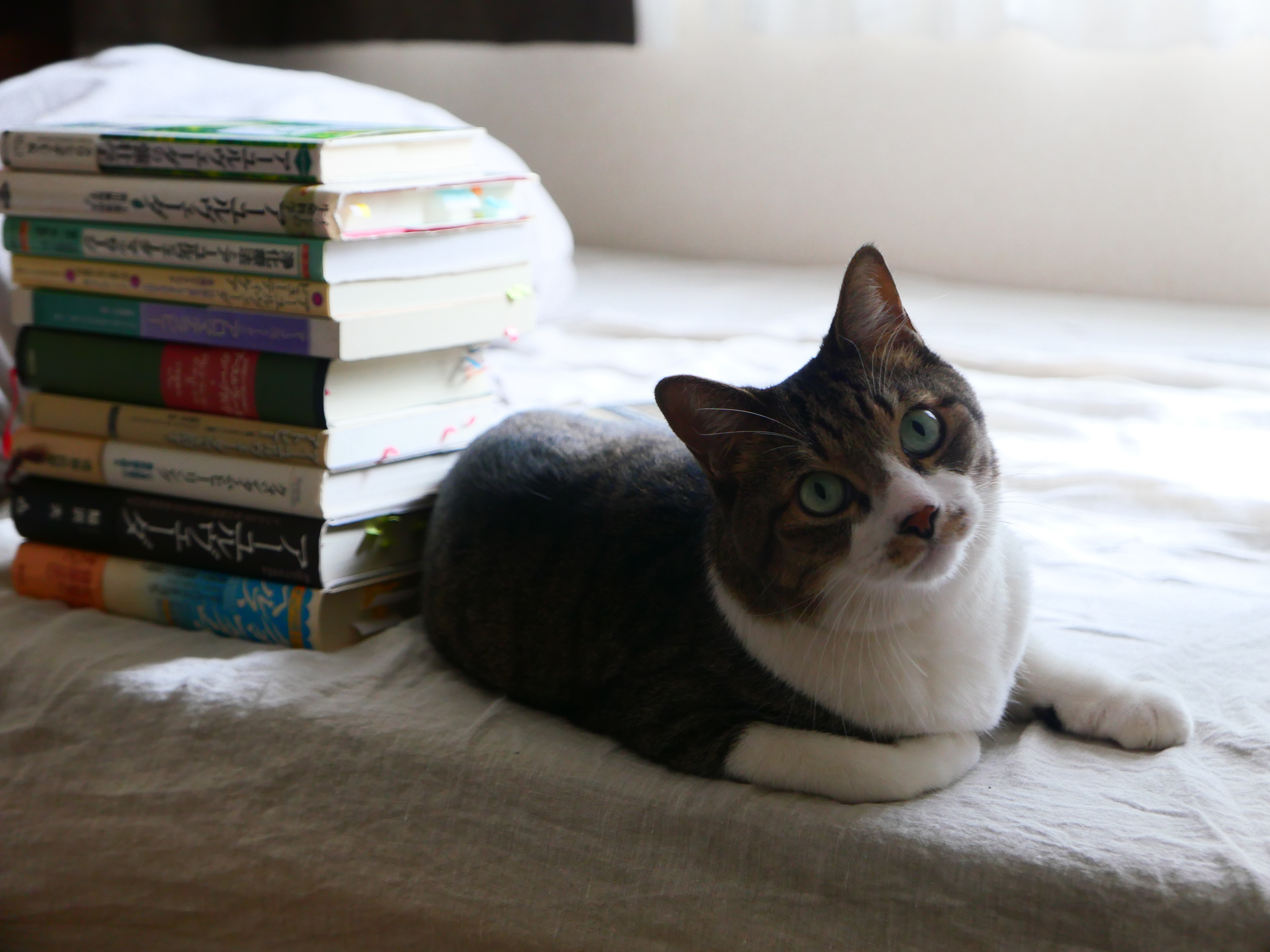
OSAJI メイクアップコレクション ディレクターのAYANAです。このコラムでは、私の創造性や価値観を支え、育ててくれた本や道具を取り上げてご紹介しながら、OSAJIというブランドを通して伝えていきたい美意識のようなものについて、お話できたらと思っています。
ビューティライター
AYANA
第2回
アーユルヴェーダ

いつ私がアーユルヴェーダというものに惹かれたのか、あまり記憶がない。大学でインドの文化を勉強していたとき、アーユルヴェーダはまだ日本でほとんど知られていなかったと思うし、授業にも出てこなかった。ちなみに当時はギリギリ20世紀、ヨガスタジオだってなかった時代で、当時日本でヨガと検索すると、山奥の寺院で修行しているおじさんのウェブサイトしかヒットしなかった記憶がある。もちろんスマホなどない。
話を戻して、おそらく20代後半に、オーガニックコスメやホリスティックビューティの世界に足を踏み入れたので、その一環で知ったのだろうか。2006年には自由が丘のスクールにアーユルヴェーダを学びに行き、2012年からはアーユルヴェーダ書籍の仕事に編集協力で10冊以上関わらせていただいた。こうしてみると、大学で勉強するならインドのことかなぁとうすぼんやり考えた高校生の自分は、あながち間違ってなかったような気になる。
アーユルヴェーダというと「体質を3つのタイプに分けるやつ」「オイルをおでこに垂らすやつ」とイメージされる方も多いかもしれない。しかしそれらはごくごく一部。実際は「真の健康とはなにか」をひろく説く学問であり、食事法や一日の過ごしかた、五感の使いかた、瞑想、運動、マッサージ法から、生命観、生きかたの知恵まで、人間を包括的にみるもの。一生をかけても学び終えることはなさそうな、壮大でありがたい知識の集積なのである。アーユルヴェーダは「生命の科学」と訳されることが多いが、哲学ではなく科学であることがポイントだなぁと個人的に思っている。
アーユルヴェーダに教わったことは本当に数えきれないほどある。おかげで私は生きるのがずいぶん楽になったと思う。人はなぜ生まれてくるのか?などと幼少期から考えがちだった私に対し、アーユルヴェーダはかなり明快に答えを提示してくれる。崇高な精神論だけではなく、日々の実践に紐づいているところもすごくいい。
たとえば「人にはそれぞれ生まれ持った性質(ドーシャ等)があるが、生活習慣等で特定の性質が乱れやすくなる。その乱れを整えて、生まれ持ったバランスに調律していくことで健康になれる」という考えかたは、人にはそれぞれ個性があるよねという多様性の真理を端的に説明している。ここでいう性質には、体質だけでなく心のことも含まれる。感じかたが人によって違うのは、ドーシャが違うからなんだなと思うと納得してしまう。自分が陥りやすい精神の落ち込みなども、ドーシャの乱れに当てはめると理解できることが多い。
あるいは「人にはそれぞれ生まれ持った役割(ダルマ)がある」というのも、とても好きな考えかただ。人は誰もがその人にしかできない才能を持っていて、それを発揮することで人生をさらに幸せなものにしていくことができる。例外なく、誰にでもその人だけのダルマがあるのだ。こんなに励みになることがあるだろうか。
人それぞれに、持って生まれた魅力と、それを開花させるための場が用意されている。だから自分自身の心地よいバランスを探し、維持する努力をしていこう。こういった考えかたは、OSAJIのメイクアップ哲学にもずいぶん反映されていると思う。あなたらしさを大切にするということ。それは個性の尊重であり、探求である、といった感じだろうか。
アーユルヴェーダを知って20年以上経つが、知識への信頼は一切揺るがない。私は敬虔なアーユルヴェーダ実践者ではないけれど(マッサージなどはほぼやらないし、肉も冷凍食品も食べる)、そんな人間にもアーユルヴェーダはいつだって門を開いてくれていて、やりたいことだけやればいいよと言ってくれる(おそらく)。そんな寛大さも好きなところのひとつだ。
写真は、かつてスクールで勉強していたときの資料と、こんなに買わなくてもよかったのでは?って感じのアーユルヴェーダ本のラインナップ。
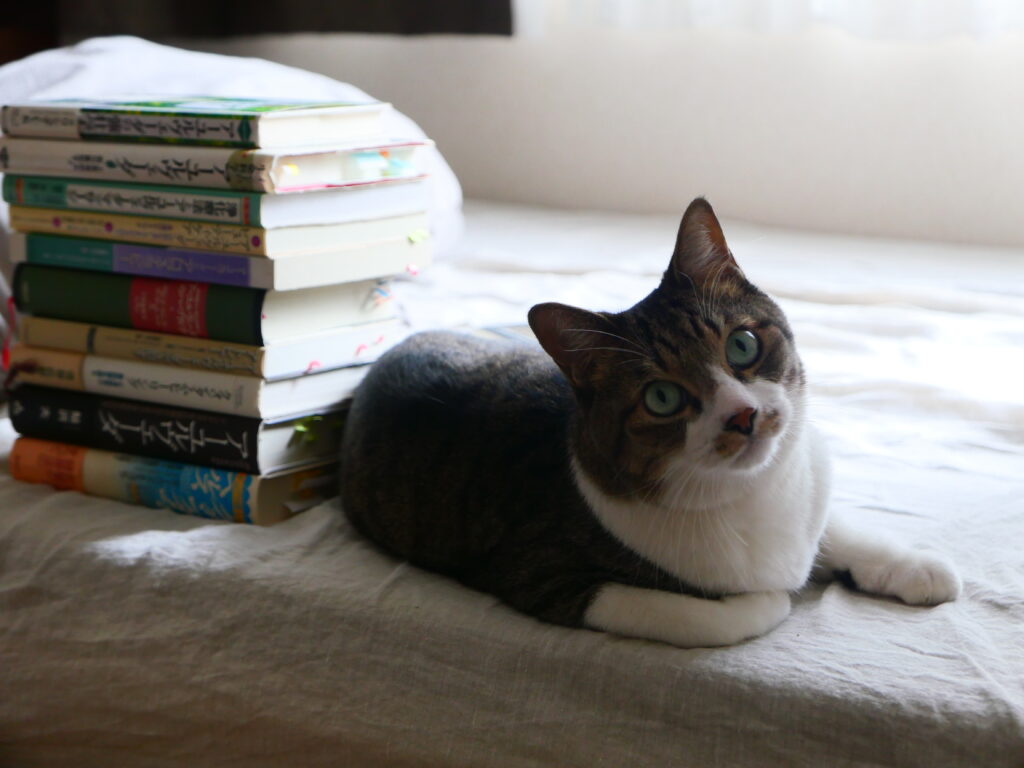
PROFILE
AYANA
ビューティライター
化粧品メーカーで商品開発に携わっていた経験を活かし、アートやウェルネスの観点からも美容を見据えるビューティライター。女性たちが自分自身や世界を美しく捉えなおすきっかけをつくるため、ライティングにとどまらず、ブランディング等の分野でも活躍する。エモーショナルな文章を書くメソッドを体系化した文章講座「EMOTIONAL WRITING METHOD」を主宰し、著書に『「美しい」のものさし』(双葉社)がある。2019年より、OSAJIメイクアップコレクションのディレクターとして参画。
https://ayana.tokyo/
連載タイトル
『需要・受容・樹葉』
3つの「じゅよう」を並べました。
需要:求めること、ほしいもの。
受容:受け入れること、肯定すること。
樹葉:幹の先、枝の先に生まれる葉。表現・創造されたものたち。
私たちは人生を通して、3つの「じゅよう」を味わい、たのしむのではないでしょうか。求めることをたのしみ、受け入れ認め合うことをたのしみ、そして自分や他者の表現をたのしむ。私個人の「じゅよう」が、誰かの「じゅよう」に繋がり、重なり、変容し、また別の「じゅよう」が生まれていく、そんな連鎖を夢想しながら、文章を綴っていけたらと思います。